
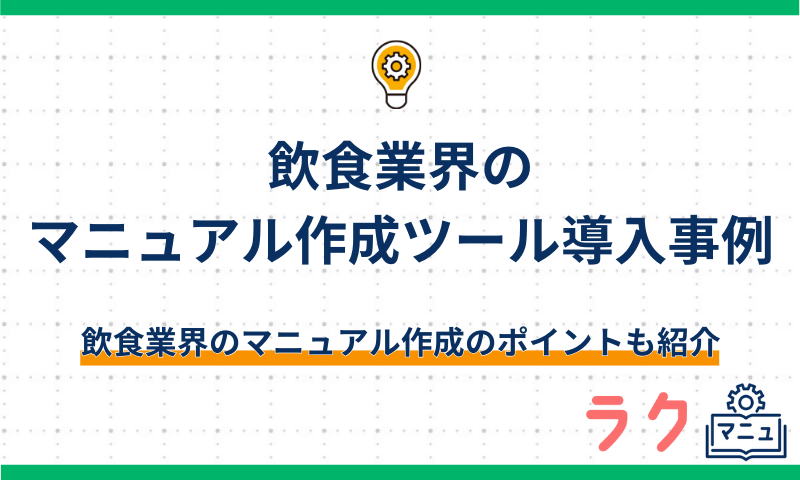
飲食業界におけるマニュアル作成は、業務の標準化やスタッフ教育の効率化に寄与しています。各企業が導入したマニュアル作成ツールの事例を通じて、現場の課題を解決し業務改善を実現した様子を見ていきます。

飲食店でマニュアルを作成すると、サービス品質を平均化することができます。サービスを提供するにあたってのルールを定めておくことで、スタッフ個人の判断ではなく、共通の認識を持って業務を進められるようになります。スタッフそれぞれの判断に委ねてサービス提供を行っていると、提供する内容や品質に差が生まれてきやすくなります。
マニュアルを作成し、業務の進め方について決まりを定めてその内容を周知することによって、スタッフごとのサービス内容の差を縮めることができます。サービス品質が一定になるため、顧客満足度の向上が期待できます。
マニュアルを用意することにより、新人スタッフが入ってきた場合の教育を効率化できます。特に、アルバイトが多くスタッフの入れ替わりが多い場合、新人教育を行う際の負担は大きくなります。
マニュアルが用意されていれば、指導しなければならない内容を全て口頭で説明する必要がなく、効率的に教育を実施できます。さらに、これまで新人教育にかけてきた時間を別の業務に充てられ、より業務効率のアップにつなげることが可能です。
スタッフ全体で共通の認識を持つためにも、マニュアルは有効といえます。新しく入ったスタッフ以外にも、マニュアルが用意されていれば自分の都合の良い時間に学習できるので、あらためて業務フローを正しく把握することが可能です。わからない業務が出てきたとしても、マニュアルがあれば簡単に確認できます。
飲食店においては、接客の質が非常に重要になるので、接客マニュアルの作成が必要です。接客マニュアルの内容としては、下記のような内容が挙げられます。
身だしなみや言葉遣い、心構えなどに関することがらをマニュアルとしてまとめていきます。お客様の来店時や料理の提供時、会計時といったように、場面ごとに細かく分けることで、わかりやすいマニュアルになります。
飲食店では、キッチンにおけるマニュアルも作成の必要があります。キッチンマニュアルには、下記のような内容をまとめます。
調理に関することや使用する食材などについての内容をマニュアルにまとめていきます。さらに、繁忙期などの対応やイレギュラーな場合の対応についてまとめておくと、業務の効率を上げられます。
もしトラブルが発生した場合にどのように対応するか、といったケースに備えたマニュアルも必要となります。こちらのマニュアルの内容としては、下記のようなものが想定されます。
店舗を運営する上で、トラブルは避けて通ることができません。また、トラブルにどう対応していくかはお店の信頼に関わってくる部分なので、対応方法を細かくまとめておくことで従業員の不安を和らげられます。
飲食業界において、業務の効率化やサービス品質の向上を目指すためには、マニュアルの整備が欠かせません。多くの企業が業務の標準化や人材教育の効率化を目指し、マニュアル作成ツールの導入を検討しています。適したツールを選ぶには、さまざまな要素を考慮する必要があります。
飲食店では、日々の業務が忙しく、スタッフが手軽に操作できるツールが求められます。
現場スタッフが複雑な操作を強いられるようなツールでは、導入後に結局使いこなせない問題が発生します。タブレットでどこからでもマニュアルを見ることができる、シンプルで分かりやすいインターフェースなどであれば、忙しい飲食店の現場でも円滑に利用できるでしょう。
飲食業界では、スタッフへの教育が頻繁に行われます。多店舗展開を行っている場合、すべてのスタッフに均一の指導や研修を行うことに苦戦している飲食店も多いのではないでしょうか。
そのような場合、教育効率を高める機能を備えたツール選びが重要です。具体的には、動画や画像を簡単に挿入できる機能や、フローを視覚的に整理できるレイアウト、さらに作成したマニュアルを即座に共有し、スタッフがスマートフォンやタブレットで簡単にアクセスできる仕組みなどです。
このような多機能性を備えたツールを導入することで、教育にかかる時間やコストを削減しながら、現場のパフォーマンス向上を目指せます。
飲食店では、メニューやサービス内容の変更が頻繁に発生します。そのため、マニュアルも定期的に更新する必要があります。
ワークフローが上手く設定できなかったり、ツールだけで更新の確認が簡単に出来ないようであれば、マニュアルの更新が遅れ現場のミスや混乱につながる恐れがあります。内容の修正、確認、承認までスムーズに作業ができるかチェックしましょう。
飲食業界でマニュアル作成ツールを導入するなら、現場での使いやすさ、更新の容易さ、教育の効率化に重点を置くと、使い続けられるマニュアルとなるでしょう。加えて自店舗の特性に応じて、動画や画像が効果的に使えるかやフローを視覚的に整理しやすいツールであるかなどの判断も必要です。
このサイトは、マニュアルを作っても使われない・伝わらない状態を解決すべく、浸透するマニュアルが作れるおすすめのツールをまとめたサイトです。「問い合わせ対応」「ノウハウ共有」「新人の教育」の用途別に適したツールを紹介していますので、ぜひご覧ください。
マニュアルの形式が作成者ごとに異なり、統一性が欠如しているという課題を抱えていました。また、作成したマニュアルが効果的に共有されず、スタッフが閲覧しない状況が続いていました。
その結果、スタッフからの問い合わせが多く、本部への負担が増大。さらに、紙のマニュアルはキッチンでの水濡れなどにより使いづらく、現場での運用に不便さがありました。
直感的な操作で統一されたマニュアルを簡単に作成・共有できるようになりました。これにより、スタッフが必要な情報を迅速に検索・閲覧できる環境が整備され、問い合わせ対応の負担が軽減。
さらに、デジタル化によりタブレットでのマニュアル閲覧が可能となり、紙の不便さも解消されました。これらの変化によって、業務の標準化が進み、業務効率の向上とスタッフ間の情報共有がスムーズに実現しました。
6店舗運営するカフェでは、各店舗には紙のマニュアルがありましたが、提供するサービスや価格の違いから、それぞれが運用しやすいようにカスタムしたことで、店舗ごとに内容が少しずつ内容が異なっていました。
結果、アルバイトが別の店舗でヘルプとして働く際や、社員が異動する際に、ルールの違いで混乱が生じました。
、動画とテキストを組み合わせたマニュアルを作成しています。これにより、視覚的にわかりやすいマニュアルが実現しました。シンプルで使いやすいため、現場でスムーズにマニュアルの利用が進んでいます。
今後は、社員向けマニュアルやスタッフ教育の効率化にもっと利用していきたいと考えています。
事業を拡大していくにあたって、店舗数が7・8まで増えたときに店舗や個人によって味や接客が違うなどの課題が出てきました。
マネージャーがチェックや指導をするも、根本的な解決や再発防止に至らずマニュアル化の取り組みを開始しました。
店舗での調理手順を統一し、一定以上の品質で提供できる仕組みづくりができたのは嬉しいです。長い時だと250時間かかっていた教育も、半分まで短縮できました。
教育時間を短縮することによって、早期の戦力化はもちろん、よりお客様に喜んでいただけるようなサービスに時間を割くこともできるようになりました。
店舗の状態や業務の実施状況を確認するために紙のチェックリストを使用していたため、都度店舗に足を運び、指示や確認を行う必要がありました。さらに、作業の実施時間が頻繁に変更になるものなどは、管理する上で変更内容を電話でやりとりするなど手間がかかっている状況でした。
そして紙でのチェックを行う場合、作業が終了したかどうかは電話で聞く・チェック済みの用紙を写真などで送ってもらう必要があったことからも、チェック・対応をもっと効率的に行いたいという希望がありました。
クラウドでの管理が行えるようになったことで、リアルタイムで業務の実施状況が見られるようになり、都度店舗に足を運ぶ必要がなくなりました。さらに、システムを導入してから店舗の接客や清掃などのレベルが上がり、良い状態を維持できる時間帯が増えるなどの効果も得られています。
老舗の寿司店での事例です。創業時から教育に力を入れていたものの、店舗でのOJTが中心の状況。マニュアルの作成はしていたものの、職人の世界ということもあり、心を受け継いでいくような形で行っていました。そのため、「板前」と呼ばれるまでには10年ほどかかっていました。
企業内研修を開講し、3〜4年で板前になれるようにカリキュラムを作成。さらに、UMUのAIコーチングを利用し、接客を学んでいます。このシステムの導入により、お客さまに価値を感じてもらえる接客を目指して人材育成を行っています。
飲食業企業がマニュアル作成ツールを選ぶ際には、使いやすさ、多機能性、既存システムとの連携、そして継続的な更新のしやすさを考慮することが重要です。これらのポイントを押さえたツールを導入すれば、業務の効率化や教育の質向上が期待できます。適切なツールを活用することで、サービス品質の向上やスタッフの育成に大きな効果をもたらすでしょう。
このサイトは、マニュアルを作っても使われない・伝わらない状態を解決すべく、浸透するマニュアルが作れるおすすめのツールをまとめたサイトです。「問い合わせ対応」「ノウハウ共有」「新人の教育」の用途別に適したツールを紹介していますので、ぜひご覧ください。
マニュアル関連でありがちな課題に沿って、目的別におすすめのマニュアル作成ツールをまとめました。ツール選定で悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

社員に使われるマニュアルで
問い合わせを生まない

自発的なノウハウ共有が
活発になる

習得状況の管理で
指導漏れ防止を実現